静岡県焼津市で100年続く老舗企業である橋本組は、公共工事・民間工事・住宅など幅広い領域で建設業を展開しています。同社は、日本全国を拠点に成長を続け、1922年にベトナムに進出しており、静岡県を代表する企業でもあります。
建設業界は、2024年4月から働き方改革関連法が適用開始されるため、労働環境の課題を解決し、是正することが求められています。今回は、世界を舞台に事業成長を加速させるべく、職場環境の革新を続ける代表取締役の橋本さんに、2024年問題に対して実施されている取り組みやワークスタイル DXツール「Acall導入」の導入効果についてお話を伺いました。
建設業の「2024年問題」、業務効率化にAcallは必要不可欠だった
- 導入のきっかけについて教えてください。

建設業界の「2024年問題」に向けた対策を検討し始めたことが大きなきっかけです。
弊社では、2020年から3年という月日をかけて、少しずつ対策を行ってきました。
その一環として2022年に完成した新社屋への引っ越しを機にフリーアドレス制を採用し、効率的な運用に向けてAcallを導入しました。
関連記事:https://www.workstyleos.com/cases/o3kv70--d7/
※建設業界の2024年問題とは、2024年4月1日に建設業が5年間猶予されてきた働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が適用されることで労働環境の変革が求められている状況のことを指します。
迫りくる2024年問題に対応するために、建設業界では早急な取り組みが必要とされています。具体的には、長時間労働を是正することや、ITツールを導入すること、技能に見合った給与を支給すること、福利厚生などの各種手当を充実させることなどが、対策として挙げられます。
フリーアドレス制がペーパーレス化を後押し、脱炭素にも寄与
- Acallの導入効果について教えてください。

① スポット(座席)チェックイン機能を活用してフリーアドレス制を運用
1番の目的は、フリーアドレス制の運用によって負荷のかかる管理部門の業務負担軽減でした。フリーアドレスによる座席の管理は、スプレットシートやホワイトボードなどで管理する企業も多いようですが、Acallを使用することで座席位置を管理する手間が省けます。
また、完全フリーアドレス制の課題となるのは、「誰がどこにいるかわからない」ため、居場所を探すのに時間がかかってしまい、非効率が生まれることです。Acallを使用すれば、居場所を確認する手間が軽減されます。フリーアドレス制を導入したことで、新入社員入社時の椅子や机、備品等の準備も不要になったことで、費用的にも時間的にも工数を削減することができました。
そもそもフリーアドレス制の導入は、社内コミュニケーションの活性化が目的でした。コミュニケーションの活性化によって部署間の隔たりがなくなり、生産性が向上したことも大きな成果の一つです。
副次的な効果として、フリーアドレス制の運用においては、キャビネットに書類を保管することができないため、ペーパーレス化の実現にも繋がりました。Acallが欠けていたらペーパーレスでのオフィス運用は実施できなかったのではないかと感じています。
何より、ペーパーレス化の取り組みが脱炭素経営にも寄与していることは間違いありません。
②会議室チェックイン機能で会議室や応接室を効率よく活用
どこの会社にもある問題かと思いますが、会議室を予約したのに使用されていないというケースも多く見受けられます。Acall導入前は、管理部門の担当者が会議室を1つ1つ回って、実際に使われているか空いているか目視で確認していたため、業務の負担となっていました。Acallの会議室チェックイン機能を活用することで、使われていない会議室は自動キャンセルされるため、効率よく会議室や応接室を活用できています。
現場でもシステムを運用できるよう、iPad端末を導入し業務の効率化を目指しました。
また、仕事の中身そのものに対しても分析を行ったところ、工事が始まる前と終わる直前が非常に忙しいことが明確になりました。
工事が始まる前と終わる直前に技術や人間を投入することによって、1人当たりの業務負担を削減できるため、そういった業務を支援するセクションを専門に作り、そこで現場の支援を行うようにしました。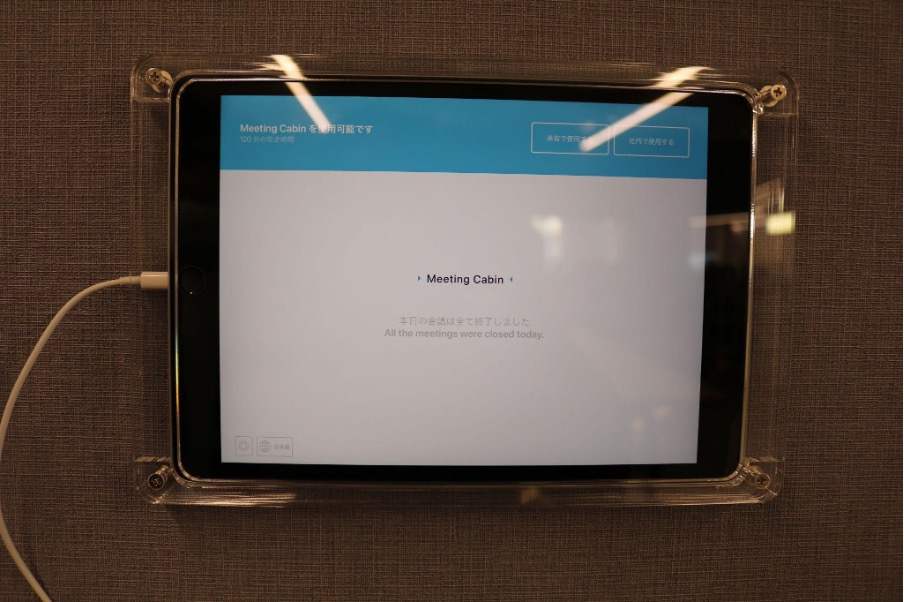
- 2024年問題に向けた対策を教えてください。
2023年度の1年間は「超働き方改革」というチームを発足し、働き方改革関連法を達成するためにプロジェクト化して社をあげて取り組んできました。プロジェクトメンバーは、弊社の中でも最も忙しいスタッフを集め、「君たちの仕事を減らすことが目的だ」と伝えました。そこから、人の手を使わなくてもできるように、様々なアプリケーションやソフトウェアを導入していきました。
近年、建築業界の課題である人手不足やアナログ作業を解消するためにDX化が注目を集めています。弊社でもICTに関連する機械を導入したり、請求書の発行の自動化システムを稼働したり、契約を全て電子契約に切り替えるといった対策を進めています。また、これまでは紙ベースで行っていた請求作業についても、取引先にもご協力いただき、電子化するシステムを2024年4月から稼働予定です。
- 今後、どのように建設業界の働き方改革を実現していくのでしょうか。
建設業界においては、土曜日仕事をするのは当たり前という世界だったと言っても過言ではありません。会社として週休二日制を謳っていたとしても、現場は別物とされており、それが最も大きな問題でした。
弊社のような施工管理では、やろうと思えばできましたが、職人さんたちの給与体系は日給月給なため、結局出勤しなければ給料がもらえない、すなわち土曜日が休みになってしまうと直接の収入減につながってしまうという問題がありました。それを逆に言い訳や大義名分にして、私たちは職人さんたちが困らないように土曜日仕事をやらなければいけないんだというような理屈が建設業界にまかり通っていました。
まず、弊社がそれを変えるために取り組みを行うべきだ、と考えました。
弊社の協力会社である、職人さんを抱えている専門工事業社には給与制度を月給制度に変えてもらえないか、と働きかけました。
弊社では、完全週休二日制を徹底しており、例えば、土日にお客様が休みの時にメンテナンスの仕事をする場合には、月火を代休にするようなシフト体制を組んでいます。とにかく1週間のうち、2日は出社しない、現場に出ないといったことを徹底するようにしています。
4月1日からは、橋本組での現場は原則的に完全土日休みにするために、現場をアンロックアウトして中に入れないようにするなどといった働きかけを行っています。
すでに国土交通省や県や市が発注者である場合の土木系の現場に関しては、原則土曜日は仕事をしない形式にしており、これはほぼ達成できてます。ただし民間工事で、例えば店舗の開店で絶対に間に合わせなければいけないというような場合では、完全週休2日で工程を組むと開店には間に合わなくなってしまうこともあったため、そこについてはやりきれていませんでした。
しかし、4月1日より私たち建設業界においても働き方改革が適用されますので、新規の案件に関して見積もりの段階から完全週休2日を徹底しています。例えば、10月1日までに仕上げて欲しいという内容で入札の案内をいただいたとして、完全週休2日にした場合が12月1日でないと間に合わない、それでも10月1日がご希望であれば私たちはこちらの案件を辞退しますとお伝えするような営業方針にしています。
このような営業方針では、受注が減ってしまうのではないか、という意見もあり、社内で議論が行われました。しかし、その仕事を受けることによって協力会社の方たちの信頼を裏切るようなことをしたら会社の存続自体が危ぶまれます。そのため、弊社は完全週休2日が守れない現場に関しては一切受注はしないという王道の方法を採用しています。
ただし、先日の能登半島地震のような場合には休まず全て対応するという意思を持っていますし、社員一人一人もそのような意識を持ってくれています。
- 建設業界の2024年問題に向けて、会社に変化はありましたか?

働き改革に真正面から取り組む前は、土曜日は会社に10人ほどは出勤していました。しかし、現在は3人ほどに減り、日曜日においては誰も出社していない状況になりました。2024年問題に対する大半の準備はできていると考えています。しかし、建設業界という観点では弊社だけの取り組みでは困難です。下請け会社を含めて、建設業界が一つになって抜本的に解決できない限りは、2024年問題の対策として万端とはいえません。
語弊があるかもしれませんが、現在の日本では能力がなくても長時間働くほど給料がたくさんもらえるということが公的に認められています。そのため、能力があるが故に短時間で仕事を終わらせることができる人員から辞めていってしまうのが現状です。
私たちは「超働き方改革プロジェクト」の中で、結果主義・成果主義の人事制度を抜本的に改革しました。マネージャークラスは結果主義、それ以外は成果主義という給与体系になっています。
弊社の働きかけによって、何社かの協力会社は日給月給をやめて完全月給制に切り替えてくれました。日給月給を月給制度に移行するとなると、時給換算した際に賃上げをしなければどこかに弊害が起きかねません。
生産性を向上し、月給制度に移行することが2024年4月以降の建設業界においては、必要不可欠だと考えています。これからは、協力会社への啓蒙を含め、建設業界へ浸透させていく活動を行っていきたいと思っています。

.JPG?w=1480)